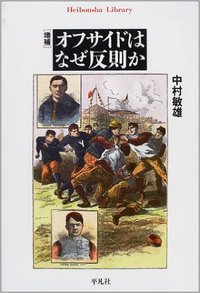しーぶん=おまけ
2012年03月10日
以前までは、ジャ○コさんやサ○エーさんといった大型ショッピングセンターで買い物を済ませることが多かったです。
結構な方々が、このような買い方をしているでしょう。
当然、何度も買い物に行っている時間がないとか、買いたいものが一ヶ所で殆どそろうとか、車でののりつけが簡単であるとか、いろいろと理由はあるでしょう。
しかし、私は最近、地元商店街(名護公設市場)の利用にウエイトを移しました。
それは、市場ならではの新鮮さと専門とする商品の種類の多さ(鮮魚店や八百屋など)、さらには地産地消を実践できるところでしょうか。

さて、こうした理由に付け加えて、私が楽しみにしているのが、沖縄方言でいう「しーぶん」。
いわゆる“おまけ”のことなんですが、市場に何度も通って、顔なじみになると、売り上げに貢献してくれているというお礼も含めて、このおまけの特典が付いてきます。
たとえば、いつもいく肉屋さんで、次のような商品(スキヤキ用牛肉¥1000、チーズ巻きフライ¥500)を購入したら、しーぶんが次のように付いてきます。

しーぶんといっても、ちょっとしたものじゃないですよ。
かなりの量のしーぶんです。

正直、おおすぎると思うときもあるくらいですから…。
しかし、このようなしーぶんは、ただ単に常連客をつなげるための手段だけではないと考えています。
こうした行為は、販売側と顧客とのコミュニケーションの活性化にも繋がっているだろうし、買い物という消費行為に大型ショッピングセンターでは感じることができない“味わい”というスパイスを付け加えます。
さらには、それが精神衛生上もプラスの方向の影響を及ぼしていると私は感じます。
残念ながら、
(1)市街地の地価の高騰による住宅地の郊外への移転
(2)モータリゼーションの進行
(3)小売店主が魅力ある商品やサービスができていない等
の様の様々な要因により、こうした地域の商店街が衰退しています。
しかし、こうした地域商店街衰退の大きな要因は、マクロ経済の大きな変化にあると思われます。
一番大きな変化といえば、2000年に施行された「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)により、それまでの大型小売店の出店規制が廃止(“大店法”廃止による)されたことが大きな要因です。
その結果、郊外に相次いで大規模スーパーなどがオープンしました。欧米などの有力スーパーも日本進出をはたすことになりました。
さて、小さな小売店を保護する目的も併せ持っていた大店法とは、どのような法律だったのでしょうか?
そして、その法律は、どのような経緯で廃止され、「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)が成立したのでしょうか?
大店法は、1973年10月1日制定、1974年3月1日施行の法律です。
目的は、「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ること」とされます。
こうした“中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ること”を目的とした法律が改正されるきっかけを作ったのは、現在うりあげを伸ばしている国内の大手流通業界・ショッピングセンターではありません。
この法律の改正大きく関与しているのは、日米貿易摩擦に絡む「日本市場の開放を求める米国の外圧」でした。
日米の貿易格差を縮小する目的で行われた日米構造協議において1990年に米国が「大規模小売店舗法(大店法)を地方自治体の上乗せ規制を含めて撤廃すべきだ」と要求したことがきっかけです。
ここでは、当時、設立されたばかりの日米合弁会社である“日本トイザらス”が国内第1号店として新潟市への出店を計画していましたが、大型店の出店に反対する地元商店街の意向を受け、その結果、事実上の大型店出店凍結により進出の見通しが全く立たないままであったことが大きく影響しています。
こうした自体の中で、米国は日本のこうした法律自体が“非関税障壁”に当たり、自由貿易の原則に反するものであり、規制緩和によって、適正な状態にするべきだとする政治的圧力をかけました。
こうした流れの中で発表された日米構造協議の中間報告で「現行大店法の枠組みの中で法律上実施可能な最大限の措置である下記の運用適正化措置を実施する」として出店調整処理期間の短縮や出店調整手続き・機関の明確化・透明化、地方公共団体の独自規制の抑制が合意されました。
さらには、翌年1991年に行われた大規模小売店舗法(大店法)の改正でこれまで商工会議所(商工会)に置かれて大型店の出店を扱っていた商業活動調整協議会(商調協)が廃止されることとなりました。
これ以降、大店法の運用は大幅に緩和され各地で大規模なショッピングセンターの進出が進むこととなった訳です。
沖縄にもこの時期に、トイザらスが嘉手納にオープン(1992年)しましたね。
(トイザらス嘉手納店は、2003年に沖縄市の旧ハイパーマートに移転しました。)
長くなりましたが、こうした大きな逆風に立ち向かい現在まで経営を続けてきた地元の商店街の皆さんの努力にも敬意を称して、さらには、一方的な消費活動ではなく、相互コミュニケーション型の消費活動を目指し、一番は、しーぶんを楽しみに、これからも地元商店街での買い物を率先していきたいと思います。
結構な方々が、このような買い方をしているでしょう。
当然、何度も買い物に行っている時間がないとか、買いたいものが一ヶ所で殆どそろうとか、車でののりつけが簡単であるとか、いろいろと理由はあるでしょう。
しかし、私は最近、地元商店街(名護公設市場)の利用にウエイトを移しました。
それは、市場ならではの新鮮さと専門とする商品の種類の多さ(鮮魚店や八百屋など)、さらには地産地消を実践できるところでしょうか。

さて、こうした理由に付け加えて、私が楽しみにしているのが、沖縄方言でいう「しーぶん」。
いわゆる“おまけ”のことなんですが、市場に何度も通って、顔なじみになると、売り上げに貢献してくれているというお礼も含めて、このおまけの特典が付いてきます。
たとえば、いつもいく肉屋さんで、次のような商品(スキヤキ用牛肉¥1000、チーズ巻きフライ¥500)を購入したら、しーぶんが次のように付いてきます。

しーぶんといっても、ちょっとしたものじゃないですよ。
かなりの量のしーぶんです。

正直、おおすぎると思うときもあるくらいですから…。
しかし、このようなしーぶんは、ただ単に常連客をつなげるための手段だけではないと考えています。
こうした行為は、販売側と顧客とのコミュニケーションの活性化にも繋がっているだろうし、買い物という消費行為に大型ショッピングセンターでは感じることができない“味わい”というスパイスを付け加えます。
さらには、それが精神衛生上もプラスの方向の影響を及ぼしていると私は感じます。
残念ながら、
(1)市街地の地価の高騰による住宅地の郊外への移転
(2)モータリゼーションの進行
(3)小売店主が魅力ある商品やサービスができていない等
の様の様々な要因により、こうした地域の商店街が衰退しています。
しかし、こうした地域商店街衰退の大きな要因は、マクロ経済の大きな変化にあると思われます。
一番大きな変化といえば、2000年に施行された「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)により、それまでの大型小売店の出店規制が廃止(“大店法”廃止による)されたことが大きな要因です。
その結果、郊外に相次いで大規模スーパーなどがオープンしました。欧米などの有力スーパーも日本進出をはたすことになりました。
さて、小さな小売店を保護する目的も併せ持っていた大店法とは、どのような法律だったのでしょうか?
そして、その法律は、どのような経緯で廃止され、「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)が成立したのでしょうか?
大店法は、1973年10月1日制定、1974年3月1日施行の法律です。
目的は、「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ること」とされます。
こうした“中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ること”を目的とした法律が改正されるきっかけを作ったのは、現在うりあげを伸ばしている国内の大手流通業界・ショッピングセンターではありません。
この法律の改正大きく関与しているのは、日米貿易摩擦に絡む「日本市場の開放を求める米国の外圧」でした。
日米の貿易格差を縮小する目的で行われた日米構造協議において1990年に米国が「大規模小売店舗法(大店法)を地方自治体の上乗せ規制を含めて撤廃すべきだ」と要求したことがきっかけです。
ここでは、当時、設立されたばかりの日米合弁会社である“日本トイザらス”が国内第1号店として新潟市への出店を計画していましたが、大型店の出店に反対する地元商店街の意向を受け、その結果、事実上の大型店出店凍結により進出の見通しが全く立たないままであったことが大きく影響しています。
こうした自体の中で、米国は日本のこうした法律自体が“非関税障壁”に当たり、自由貿易の原則に反するものであり、規制緩和によって、適正な状態にするべきだとする政治的圧力をかけました。
こうした流れの中で発表された日米構造協議の中間報告で「現行大店法の枠組みの中で法律上実施可能な最大限の措置である下記の運用適正化措置を実施する」として出店調整処理期間の短縮や出店調整手続き・機関の明確化・透明化、地方公共団体の独自規制の抑制が合意されました。
さらには、翌年1991年に行われた大規模小売店舗法(大店法)の改正でこれまで商工会議所(商工会)に置かれて大型店の出店を扱っていた商業活動調整協議会(商調協)が廃止されることとなりました。
これ以降、大店法の運用は大幅に緩和され各地で大規模なショッピングセンターの進出が進むこととなった訳です。
沖縄にもこの時期に、トイザらスが嘉手納にオープン(1992年)しましたね。
(トイザらス嘉手納店は、2003年に沖縄市の旧ハイパーマートに移転しました。)
長くなりましたが、こうした大きな逆風に立ち向かい現在まで経営を続けてきた地元の商店街の皆さんの努力にも敬意を称して、さらには、一方的な消費活動ではなく、相互コミュニケーション型の消費活動を目指し、一番は、しーぶんを楽しみに、これからも地元商店街での買い物を率先していきたいと思います。
★Face bookもよろしく!→http://www.facebook.com/#!/hironobu.higa
Posted by no-bu at 09:16│Comments(1)
│日常の生活
この記事へのコメント
んー
なるほど!
勉強になりました!(^-^)
なるほど!
勉強になりました!(^-^)
Posted by 青学 at 2012年04月13日 09:29