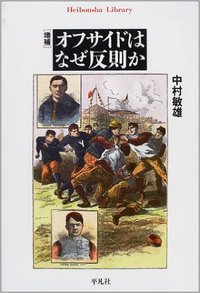ピロリ菌との長い長い闘い
2015年11月25日
ひさしぶりのブログアップです。
いやー、長い戦いがようやく本日終わりました。
ピロリ菌との過酷な戦いです。
私の胃の中にピロリ菌が発見されたのが、ちょうど二年前の人間ドックの時でした。
人間ドックでは、一年に一回かならず胃カメラ検査をするようにしています。
二年前の胃カメラでお医者さんから「胃が若干あれているからピロリ検査してみる?今年から保険適用になったし」といわれ、検査をしてからでした。
少し前までにピロリ菌による胃がんリスクの増大に関する記事を読んだことはありましたが、その時までは、あまり周りにピロリ菌の感染の話は聞いたことがなかったので、「まさか自分にピロリ菌なんかいないわな」と思っていました。
しかし、結果は、立派な黒。
それも結構な黒らしく、お医者さんから「どうする除菌する?」と聞かれましたが、なぜかしら少しためらったあげく、「しばらく考えてからにします」と返事、それからなんとなく1年がたってしまいました。
で、今年の夏の人間ドックでまたもや医者に警告を発せられ、ピロリ菌のリスクについて重々と説明されました。
まず、「ピロリ菌は慢性胃炎や胃潰瘍になる原因の1つではなく、原因そのものである」ということ、
そして、「ピロリ菌が人体に与える主な影響は、
1.慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍を誘発する
2.胃がんになる確率が20倍以上に跳ね上がる
3.胃MALTリンパ腫といった胃の病気にかかりやすくなる。
つまり、ピロリ菌の感染が続くと感染範囲が“胃の出口”の方から“胃の入口”の方に広がって、慢性胃炎(ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)がすすみ、この慢性胃炎が、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、胃がん、さらには全身的な病気などを引き起こすおそれがある」という説明を受けました。
で、今回ばかりは、こんなにきつく説明を受けたので、「やります」と即答したのです。
そして、抗生剤をもらい1週間飲み続けた後、その2カ月後にまた、検査を受けることになりました。
さて、ピロリ菌について、あまりにも知識不足だった私は、薬の服用を始めると同時に、すぐにお勉強を始めました。
それによると、「胃の中はpH1~2と高い酸性で、とても生物が生きていけるような環境ではないが、ピロリ菌は胃酸を直接触れないように、自らが住みやすい環境を作りだしているから生息できることを知りました。
ピロリ菌はらせん状をしており、数本のべん毛を持っていて活発に動き回っており、胃の粘膜に好んで住みつき、粘液の下にもぐりこんで多くの胃酸から逃れている。
さらにピロリ菌は胃酸に耐えて抜くためにウレアーゼと呼ばれる酵素を吐き出す。
この酵素は胃粘液の成分である尿素アンモニアと二酸化炭素に分解する。
この分解された強アルカリ性のアンモニアで自分の周りを覆って、強酸性の胃酸と中和させ、胃の中の強酸性の状況下でも生きていける環境を自ら作り出している。
ここで、このピロリ菌が発生させるウレアーゼを含めた毒素が、私たちの胃粘膜に障害をもたらすことを知りました。

ピロリ菌の検査は、
(1)採血や採尿して抗体を調べる検査
(2)検査薬を服用した後に呼気を調べる検査
(3)便中の抗原を調べる検査
(4)内視鏡で直接胃の粘膜を採取して調べる検査
に大別されますが、呼気検査が一般的です。
尿素呼気試験法というものです。
尿素を含んだ検査薬を服用する前に、袋の中に呼気を採取します。
その後、検査薬を服用し、ある程度時間がたった後に、再度呼気を採取します。
その際に、両方の二酸化炭素の量で判断するわけです。
上に書いたように、ピロリ菌が、尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解することを利用した検査法です。
2013年から保険診療対象になりましたが、保険診療の枠の中で除菌するには、内視鏡検査で胃炎があることが診断されなければなりません。
私の場合は、人間ドックでの胃カメラの検査により胃炎の症状があったために保険適用となりました。
しかし、だいたいの人がピロリ菌の疑いをかけられるのが、胃カメラではないでしょうか。
私が、最初に飲んだ薬がランザップという薬でした。これには、胃酸分泌抑制薬であるPPI(プロトンポンプ阻害剤)と2種類の抗生物質であるアモキシシリンとクラリスロマイシンが含まれています。
この抗生剤の服用は、肝臓にダメージを与える可能性があるために、服用中の前後は飲酒を規制されます。
これが、一番何よりもきついのです。
しかし、にっくきピロリ菌の退治のために頑張りました。
そして、2カ月後に再度、通院し呼気検査を受けて菌が死んでしまったかどうかを検査します。
で、その結果、菌がまだ死んでいませんでした。
1回目の除菌の確率は、約70%らしいです。私は、30%の中に入って強い待ったわけです。

では、なぜ、私の菌は1回で死ななかったのか?
問題は、除菌に使うクラリスロマイシンへの耐性を獲得したピロリ菌であったということです。
風邪で医療機関を受診するとしばしば抗菌薬が処方されますが、なかでもクラリスロマイシンは幅広い種類の菌に効く抗菌薬なので、かなり多用されているようです。
その結果、知らないうちに胃の中のピロリ菌がクラリスロマイシンに対する耐性を獲得してしまっている人が少なくないということ。
ここで、苦しい二回目の菌との戦いを決意します。
今回は、1回目に飲んだクラリスロマイシンを、より強力な抗生剤であるメトロニダゾールに変えチャレンジ、9月の一番ビールがおいしい時期に、実は私は3週間も酒を断った時期がありました。
その辛さといったら。
その辛い戦いの成果もあり、本日の検査でしっかりとピロリ菌さんがいの中から撲滅されていることを確認できました。
実は、二回目のチャレンジの前に、お医者さんに二回目でも不成功になる確率はあるのですか?と質問したら、成功率は98%だから、まれに2%は不成功になる可能性もあるよといわれ、その2%に入るのではと心配していましたが、良かったです。
一度、ピロリ菌を除去すると、川の水や沢の水などの生水を飲まない限りは、二度とかからないらしいです。
これからは、注意したいと思います。
いやー、長い戦いがようやく本日終わりました。
ピロリ菌との過酷な戦いです。
私の胃の中にピロリ菌が発見されたのが、ちょうど二年前の人間ドックの時でした。
人間ドックでは、一年に一回かならず胃カメラ検査をするようにしています。
二年前の胃カメラでお医者さんから「胃が若干あれているからピロリ検査してみる?今年から保険適用になったし」といわれ、検査をしてからでした。
少し前までにピロリ菌による胃がんリスクの増大に関する記事を読んだことはありましたが、その時までは、あまり周りにピロリ菌の感染の話は聞いたことがなかったので、「まさか自分にピロリ菌なんかいないわな」と思っていました。
しかし、結果は、立派な黒。

それも結構な黒らしく、お医者さんから「どうする除菌する?」と聞かれましたが、なぜかしら少しためらったあげく、「しばらく考えてからにします」と返事、それからなんとなく1年がたってしまいました。
で、今年の夏の人間ドックでまたもや医者に警告を発せられ、ピロリ菌のリスクについて重々と説明されました。
まず、「ピロリ菌は慢性胃炎や胃潰瘍になる原因の1つではなく、原因そのものである」ということ、
そして、「ピロリ菌が人体に与える主な影響は、
1.慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍を誘発する
2.胃がんになる確率が20倍以上に跳ね上がる
3.胃MALTリンパ腫といった胃の病気にかかりやすくなる。
つまり、ピロリ菌の感染が続くと感染範囲が“胃の出口”の方から“胃の入口”の方に広がって、慢性胃炎(ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)がすすみ、この慢性胃炎が、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、胃がん、さらには全身的な病気などを引き起こすおそれがある」という説明を受けました。
で、今回ばかりは、こんなにきつく説明を受けたので、「やります」と即答したのです。
そして、抗生剤をもらい1週間飲み続けた後、その2カ月後にまた、検査を受けることになりました。
さて、ピロリ菌について、あまりにも知識不足だった私は、薬の服用を始めると同時に、すぐにお勉強を始めました。
それによると、「胃の中はpH1~2と高い酸性で、とても生物が生きていけるような環境ではないが、ピロリ菌は胃酸を直接触れないように、自らが住みやすい環境を作りだしているから生息できることを知りました。
ピロリ菌はらせん状をしており、数本のべん毛を持っていて活発に動き回っており、胃の粘膜に好んで住みつき、粘液の下にもぐりこんで多くの胃酸から逃れている。
さらにピロリ菌は胃酸に耐えて抜くためにウレアーゼと呼ばれる酵素を吐き出す。
この酵素は胃粘液の成分である尿素アンモニアと二酸化炭素に分解する。
この分解された強アルカリ性のアンモニアで自分の周りを覆って、強酸性の胃酸と中和させ、胃の中の強酸性の状況下でも生きていける環境を自ら作り出している。
ここで、このピロリ菌が発生させるウレアーゼを含めた毒素が、私たちの胃粘膜に障害をもたらすことを知りました。

ピロリ菌の検査は、
(1)採血や採尿して抗体を調べる検査
(2)検査薬を服用した後に呼気を調べる検査
(3)便中の抗原を調べる検査
(4)内視鏡で直接胃の粘膜を採取して調べる検査
に大別されますが、呼気検査が一般的です。
尿素呼気試験法というものです。
尿素を含んだ検査薬を服用する前に、袋の中に呼気を採取します。
その後、検査薬を服用し、ある程度時間がたった後に、再度呼気を採取します。
その際に、両方の二酸化炭素の量で判断するわけです。
上に書いたように、ピロリ菌が、尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解することを利用した検査法です。
2013年から保険診療対象になりましたが、保険診療の枠の中で除菌するには、内視鏡検査で胃炎があることが診断されなければなりません。
私の場合は、人間ドックでの胃カメラの検査により胃炎の症状があったために保険適用となりました。
しかし、だいたいの人がピロリ菌の疑いをかけられるのが、胃カメラではないでしょうか。
私が、最初に飲んだ薬がランザップという薬でした。これには、胃酸分泌抑制薬であるPPI(プロトンポンプ阻害剤)と2種類の抗生物質であるアモキシシリンとクラリスロマイシンが含まれています。
この抗生剤の服用は、肝臓にダメージを与える可能性があるために、服用中の前後は飲酒を規制されます。
これが、一番何よりもきついのです。

しかし、にっくきピロリ菌の退治のために頑張りました。
そして、2カ月後に再度、通院し呼気検査を受けて菌が死んでしまったかどうかを検査します。
で、その結果、菌がまだ死んでいませんでした。
1回目の除菌の確率は、約70%らしいです。私は、30%の中に入って強い待ったわけです。

では、なぜ、私の菌は1回で死ななかったのか?
問題は、除菌に使うクラリスロマイシンへの耐性を獲得したピロリ菌であったということです。
風邪で医療機関を受診するとしばしば抗菌薬が処方されますが、なかでもクラリスロマイシンは幅広い種類の菌に効く抗菌薬なので、かなり多用されているようです。
その結果、知らないうちに胃の中のピロリ菌がクラリスロマイシンに対する耐性を獲得してしまっている人が少なくないということ。
ここで、苦しい二回目の菌との戦いを決意します。
今回は、1回目に飲んだクラリスロマイシンを、より強力な抗生剤であるメトロニダゾールに変えチャレンジ、9月の一番ビールがおいしい時期に、実は私は3週間も酒を断った時期がありました。
その辛さといったら。
その辛い戦いの成果もあり、本日の検査でしっかりとピロリ菌さんがいの中から撲滅されていることを確認できました。
実は、二回目のチャレンジの前に、お医者さんに二回目でも不成功になる確率はあるのですか?と質問したら、成功率は98%だから、まれに2%は不成功になる可能性もあるよといわれ、その2%に入るのではと心配していましたが、良かったです。
一度、ピロリ菌を除去すると、川の水や沢の水などの生水を飲まない限りは、二度とかからないらしいです。
これからは、注意したいと思います。
★Face bookもよろしく!→http://www.facebook.com/#!/hironobu.higa
Posted by no-bu at 13:17│Comments(0)
│日常の生活