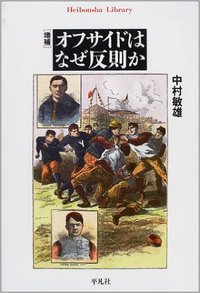映画「赤ずきん」(洋画)
2012年01月28日
さ~て、今日は長くなりますよ~。
心してくださいね。
時間ない方は、次の機会にどうぞ。
さて、皆さんは有名なグリム童話「赤ずきん」覚えていますか?
とりあえず確認しておきましょうね。
 (グリム童話 赤ずきん)
(グリム童話 赤ずきん)
おばあさんからもらった赤びろうどの頭巾しかかぶらないことから赤ずきんと呼ばれた女の子がいた。
ある時、赤ずきんはお母さんから、森の奥に住むおばあさんにお菓子とぶどう酒をもってお見舞いに行くよう頼まれる。
赤ずきんが、朝早く家を出て歩いているとオオカミと会い、どこに行くのか聞かれたので、おばあさんの家に見舞いに行くと話すと、オオカミは赤ずきんとおばあさんを2人とも食べてしまおうと考えた。
そこで、赤ずきんが森で花を摘んでいるすきに、オオカミは先回りしておばあさんの家に行き、まずおばあさんを呑みこんだ。
そして、おばあさんに化けてベッドで待ちうけ、後から家にやって来た赤ずきんも呑みこんでしまう。
2人を食べて眠くなったオオカミがそのままベッドでいびきをかいて寝ていると、家の前を通りかかった猟師がいびきが気になり家に入ってみると、そこに朝から狙っていたオオカミがいたので鉄砲で撃ち殺そうとしたが、膨れたおなかを見ておばあさんが食べられているかもしれないと思い、オオカミのお腹を切り開いてみた。
するとまだ生きている赤ずきんとおばあさんが出てきた。
そして赤ずきんはオオカミのお腹に石を詰込んで縫い合わせた。
オオカミは目を覚まして逃げようとしたがお腹の石が重くて倒れこんで死んでしまった。
これを見て3人は安心した。猟師はオオカミの毛皮をはぎ取って持ち帰り、おばあさんはその後赤ずきんのお菓子とぶどう酒で元気になり、いっぽう、赤ずきんは言いつけにそむいて寄り道するのは今後やめようと思った。
実は、このグリム童話には、それぞれの話の中に“教訓”が織り込まれてるようです。
とりあえず、その教訓とはつぎのようなもの…。
(教訓)
悪意を持っているかもしれない素性の分からない知らない相手に、自分のことを詳しく話してはいけない。
それがもとで被害を受けるかもしれないから…。
相手の素性や質問をしてくる背景をしっかりつかむまで自分の細かいことについて話してはいけない。
さて、よく「本当は怖い」というフレーズがついたグリム童話の話は、聞いたことがあると思います。
“本当は怖い”という意味は、このグリム童話は、もともとの原作の内容をそぎ落としたり、そこに加えて脚色をほどこしており、もともとの原作を辿ると、もっとリアルで生々しい内容なんだという意味です。
 「赤ずきん」
「赤ずきん」
監督:キャサリン・ハードウィック
制作:レオナルド・ディカプリオ
出演:アマンダ・サイフリッド,ゲイリー・オールドマン,ビリー・バーク,シャイロー・フェルナンデス,ヴァージニア・マドセン,ジュリー・クリスティ,ダーレン・シャラヴィ,マイケル・シャンクス,ルーカス・ハース
心してくださいね。
時間ない方は、次の機会にどうぞ。
さて、皆さんは有名なグリム童話「赤ずきん」覚えていますか?
とりあえず確認しておきましょうね。
 (グリム童話 赤ずきん)
(グリム童話 赤ずきん)おばあさんからもらった赤びろうどの頭巾しかかぶらないことから赤ずきんと呼ばれた女の子がいた。
ある時、赤ずきんはお母さんから、森の奥に住むおばあさんにお菓子とぶどう酒をもってお見舞いに行くよう頼まれる。
赤ずきんが、朝早く家を出て歩いているとオオカミと会い、どこに行くのか聞かれたので、おばあさんの家に見舞いに行くと話すと、オオカミは赤ずきんとおばあさんを2人とも食べてしまおうと考えた。
そこで、赤ずきんが森で花を摘んでいるすきに、オオカミは先回りしておばあさんの家に行き、まずおばあさんを呑みこんだ。
そして、おばあさんに化けてベッドで待ちうけ、後から家にやって来た赤ずきんも呑みこんでしまう。
2人を食べて眠くなったオオカミがそのままベッドでいびきをかいて寝ていると、家の前を通りかかった猟師がいびきが気になり家に入ってみると、そこに朝から狙っていたオオカミがいたので鉄砲で撃ち殺そうとしたが、膨れたおなかを見ておばあさんが食べられているかもしれないと思い、オオカミのお腹を切り開いてみた。
するとまだ生きている赤ずきんとおばあさんが出てきた。
そして赤ずきんはオオカミのお腹に石を詰込んで縫い合わせた。
オオカミは目を覚まして逃げようとしたがお腹の石が重くて倒れこんで死んでしまった。
これを見て3人は安心した。猟師はオオカミの毛皮をはぎ取って持ち帰り、おばあさんはその後赤ずきんのお菓子とぶどう酒で元気になり、いっぽう、赤ずきんは言いつけにそむいて寄り道するのは今後やめようと思った。
実は、このグリム童話には、それぞれの話の中に“教訓”が織り込まれてるようです。

とりあえず、その教訓とはつぎのようなもの…。
(教訓)
悪意を持っているかもしれない素性の分からない知らない相手に、自分のことを詳しく話してはいけない。
それがもとで被害を受けるかもしれないから…。
相手の素性や質問をしてくる背景をしっかりつかむまで自分の細かいことについて話してはいけない。
さて、よく「本当は怖い」というフレーズがついたグリム童話の話は、聞いたことがあると思います。
“本当は怖い”という意味は、このグリム童話は、もともとの原作の内容をそぎ落としたり、そこに加えて脚色をほどこしており、もともとの原作を辿ると、もっとリアルで生々しい内容なんだという意味です。
 「赤ずきん」
「赤ずきん」監督:キャサリン・ハードウィック
制作:レオナルド・ディカプリオ
出演:アマンダ・サイフリッド,ゲイリー・オールドマン,ビリー・バーク,シャイロー・フェルナンデス,ヴァージニア・マドセン,ジュリー・クリスティ,ダーレン・シャラヴィ,マイケル・シャンクス,ルーカス・ハース
グリム兄弟は、当初「グリム童話」(正式名称「子どもと家庭の童話」)をメルヘンの研究書として出版しました。
しかし、それが次第に人気を博し、版を重ねるにつれ、彼らはしだいに子どもの読者を意識するようになり、それぞれの童話を子ども向けに書き換えていったようです。
書き換えたのは、まず第一に“セクシャル”(性的)な内容を想起させるような部分を取り除いた。
二つめに、そこに加えて、童話から子どもたちが教訓を読みとれるようなものにした点。
もともと、この「赤ずきん」の原作は、民話をペローという人が童話の形にしたものらしいですが、ペロー版の原作がグリム兄弟によってどのように書き換えられているかを見てみましょう。
原作では、母親は赤ずきんにこう言う場面があります。
「おばあさまがご病気のようだから、お見舞いにいっておくれ。ガレットとこのバターの壺をもっていってちょうだい」。
この母親のセリフは、グリム版では次のように書き換えられています。
「さあ、赤ずきんや、ここにあるお菓子とぶどう酒をおばあさんのところへ持っていっておくれ。
病気で弱っていらっしゃるから、きっとこれでお元気になるよ。
暑くならないうちにお出かけ。
外に出たらお行儀よく歩いて、道草を食ってはいけませんよ。
そんなことすると、転んで、びんをこわして、おばあさんに何もあげられなくなってしまいますからね。
おばあさんの部屋に入ったら、忘れずに『おはようございます』と言うんですよ。
先に部屋の中をきょろきょろ見回したりしてはいけませんよ」。
ここに端的に示されているように、グリム兄弟は、道徳的徳目である“行儀よく歩きなさい”や“ちゃんと挨拶しなさい”などの徳目を付け加えています。さらには、“道草をしてはいけませんよ、あぶない目にあいますから”という警告までも付け加えています。これは、言い換えると、“親のいいつけを守らないと必ず酷い目に遭うよ”というメッセージを暗に発しているのです。
こうした一般に知られている「グリム童話」の内容ではなく、忠実に原作を分析してつくられたのが、今回の作品です。
本作についてハードウィック監督は、「私たちのほとんどは、道徳的でない要素をそぎ落とされたバージョンの『赤ずきん』を読んで育ったけれど、もともとのおとぎ話はもっと不穏な要素があるので遥かに興味深い。
少女が森の中に1人で入って行き、狼が彼女をつけ回し、そして話しかけるというアイデア…。
そこにはとても多くの謎が隠されていて、さまざまなレベルで想像力を刺激する。
幼い子供が読めば、このストーリーには一つの意味しかないかもしれないけれど、10代になってから、あるいは大人になってから読み返すと、まったく違う意味で惹かれる」と本作の魅力を語っています。
本作では、童話からは想像できない魅惑的な赤ずきんが…
 では、そのできばえは…。
では、そのできばえは…。
序盤はは次のように始まります。
元々昔から狼の脅威に晒されていたある村があった。
村では、今まで豚などを捧げて、被害を出さないようにしていた。
しかし、ある日のこと、狼が掟を破り、村人を襲い殺してしまう事件が発生!
何の前触れもなく掟を破った狼に怒り、その退治に向かう…。
村の神父の話によると、狼は人狼で、満月の夜意外は人の姿をしている。
そして満月がくると、狼に変身し人を襲うらしい。
それでは、村人のうち、いったい誰が人狼なのか?
村人のなかに疑心暗鬼が広がる…。
 この答えを考えながら見ていくと楽しいでしょうね。
この答えを考えながら見ていくと楽しいでしょうね。
作品が進んでいく過程で、何人か怪しい人物があがってくるんですが…。
原作の内容を知っていたとしても、なかなか一回で“狼は誰か”あてることはできないでしょうね。
ほら、もう気になってきたでしょ!
ちなみに、かつて原作のつくられた時代には、“狼=幼い子供を襲う性的な倒錯者、狂人”だったようです。
12世紀頃から、この種の犯罪者は“オオカミ裁判”にかけられ腹を切り裂かれ石を詰込まれる刑を処せられていたらしいです。
ここを(心理学的に)深読みすると、父と娘の深層心理がわかるとか…ということらしいですけど、興味のある方は調べてみてください。
さらには、中世ヨーロッパで“赤を着る人=娼婦、刑の執行官、難病患者”で赤=社会の嫌われ者、忌み嫌われ者を表現したようです。
こうした点で見ていくと、赤ずきんは、最初から社会からスポイルされる存在として規定されるとみることもできます。
つまり、当時のヨーロッパは、魔女摘発の手が伸ばされ魔女裁判が盛んに行われていた時代であり、その中で赤は「罪・官能・悪魔」をイメージさせる色なのです。
そういう意味で、赤ずきんちゃんが祖母から赤いずきんを贈られるということは、赤ずきんが一般の人とは違う特殊な要素を持っている=魔女になりうる素質を持つ、ということも示していると考えられているらしいです。
本作においても、赤ずきんだけが人狼と言葉を交わす特殊な能力を持っています。
こうした一連の裏側に秘められた事実を分かった上で、童話と違う“魅惑的な”赤ずきんを鑑賞すると楽しく見れるでしょうね。
ストーリー的には大変楽しく見れたのですが、CGの作りが雑な点が気になったので、今回は…
「評価 ★★★★★ ★★☆☆☆ 70点」
(あらすじ)☆ネタバレ注意!
美しく成長した年頃のバレリー(アマンダ・サイフリッド)は、両親によって村一番の裕福な一族の跡取りヘンリー(マックス・アイアンズ)との婚約が決められたことを知らされる。
だが、彼女には幼馴染みで木こりのピーター(シャイロー・フェルナンデス)という、将来を誓い合った恋人がいた。
2人はすべてを投げ捨てて駆け落ちを決意するが、血のように真っ赤な満月の夜、すべてが一瞬にして変わってしまう。
バレリーの姉が何者かに殺されたのだ。
この村では長年に渡って、動物の生け贄を捧げることで平和を保っていたが、“それ”は協定を破ったのだ。
怒りに震え、復讐に燃える村人たちは、魔物ハンターとして名を馳せるソロモン神父(ゲイリー・オールドマン)を村に招く。
だが、やって来たソロモンは、村人たちに思いもよらぬ事実を告げる。
犯人=“それ”は満月の夜だけ狼に変わる人狼だというのだ。
“それ”は正体を隠したまま村に紛れているというソロモンの言葉によって、疑心暗鬼を募らせる村人たち。
次々に犠牲者が増えるなか、パニックに陥ってゆく。
そして13年に一度の赤い惑星と月が並ぶ夜。
血のように赤い月の下でついに“それ”は姿を現す。
そして、“それ”はバレリーに話しかける。
“俺はお前をよく知っている。一緒に来い”。
一体“それ”は何者なのか?
手がかりはダークブラウンの瞳だけ。
愛するピーターなのか?婚約者のヘンリーか?それとも……?
“それ”の目的がバレリーを連れ去ることだと知ったソロモン神父は、彼女を囮にして広場に拘束する。
危機が迫る中、ついに“それ”の正体が暴かれるが……。
しかし、それが次第に人気を博し、版を重ねるにつれ、彼らはしだいに子どもの読者を意識するようになり、それぞれの童話を子ども向けに書き換えていったようです。
書き換えたのは、まず第一に“セクシャル”(性的)な内容を想起させるような部分を取り除いた。
二つめに、そこに加えて、童話から子どもたちが教訓を読みとれるようなものにした点。
もともと、この「赤ずきん」の原作は、民話をペローという人が童話の形にしたものらしいですが、ペロー版の原作がグリム兄弟によってどのように書き換えられているかを見てみましょう。
原作では、母親は赤ずきんにこう言う場面があります。
「おばあさまがご病気のようだから、お見舞いにいっておくれ。ガレットとこのバターの壺をもっていってちょうだい」。
この母親のセリフは、グリム版では次のように書き換えられています。
「さあ、赤ずきんや、ここにあるお菓子とぶどう酒をおばあさんのところへ持っていっておくれ。
病気で弱っていらっしゃるから、きっとこれでお元気になるよ。
暑くならないうちにお出かけ。
外に出たらお行儀よく歩いて、道草を食ってはいけませんよ。
そんなことすると、転んで、びんをこわして、おばあさんに何もあげられなくなってしまいますからね。
おばあさんの部屋に入ったら、忘れずに『おはようございます』と言うんですよ。
先に部屋の中をきょろきょろ見回したりしてはいけませんよ」。
ここに端的に示されているように、グリム兄弟は、道徳的徳目である“行儀よく歩きなさい”や“ちゃんと挨拶しなさい”などの徳目を付け加えています。さらには、“道草をしてはいけませんよ、あぶない目にあいますから”という警告までも付け加えています。これは、言い換えると、“親のいいつけを守らないと必ず酷い目に遭うよ”というメッセージを暗に発しているのです。
こうした一般に知られている「グリム童話」の内容ではなく、忠実に原作を分析してつくられたのが、今回の作品です。
本作についてハードウィック監督は、「私たちのほとんどは、道徳的でない要素をそぎ落とされたバージョンの『赤ずきん』を読んで育ったけれど、もともとのおとぎ話はもっと不穏な要素があるので遥かに興味深い。
少女が森の中に1人で入って行き、狼が彼女をつけ回し、そして話しかけるというアイデア…。
そこにはとても多くの謎が隠されていて、さまざまなレベルで想像力を刺激する。
幼い子供が読めば、このストーリーには一つの意味しかないかもしれないけれど、10代になってから、あるいは大人になってから読み返すと、まったく違う意味で惹かれる」と本作の魅力を語っています。
本作では、童話からは想像できない魅惑的な赤ずきんが…
 では、そのできばえは…。
では、そのできばえは…。序盤はは次のように始まります。
元々昔から狼の脅威に晒されていたある村があった。
村では、今まで豚などを捧げて、被害を出さないようにしていた。
しかし、ある日のこと、狼が掟を破り、村人を襲い殺してしまう事件が発生!
何の前触れもなく掟を破った狼に怒り、その退治に向かう…。
村の神父の話によると、狼は人狼で、満月の夜意外は人の姿をしている。
そして満月がくると、狼に変身し人を襲うらしい。
それでは、村人のうち、いったい誰が人狼なのか?
村人のなかに疑心暗鬼が広がる…。
 この答えを考えながら見ていくと楽しいでしょうね。
この答えを考えながら見ていくと楽しいでしょうね。作品が進んでいく過程で、何人か怪しい人物があがってくるんですが…。
原作の内容を知っていたとしても、なかなか一回で“狼は誰か”あてることはできないでしょうね。
ほら、もう気になってきたでしょ!
ちなみに、かつて原作のつくられた時代には、“狼=幼い子供を襲う性的な倒錯者、狂人”だったようです。
12世紀頃から、この種の犯罪者は“オオカミ裁判”にかけられ腹を切り裂かれ石を詰込まれる刑を処せられていたらしいです。
ここを(心理学的に)深読みすると、父と娘の深層心理がわかるとか…ということらしいですけど、興味のある方は調べてみてください。
さらには、中世ヨーロッパで“赤を着る人=娼婦、刑の執行官、難病患者”で赤=社会の嫌われ者、忌み嫌われ者を表現したようです。
こうした点で見ていくと、赤ずきんは、最初から社会からスポイルされる存在として規定されるとみることもできます。
つまり、当時のヨーロッパは、魔女摘発の手が伸ばされ魔女裁判が盛んに行われていた時代であり、その中で赤は「罪・官能・悪魔」をイメージさせる色なのです。
そういう意味で、赤ずきんちゃんが祖母から赤いずきんを贈られるということは、赤ずきんが一般の人とは違う特殊な要素を持っている=魔女になりうる素質を持つ、ということも示していると考えられているらしいです。
本作においても、赤ずきんだけが人狼と言葉を交わす特殊な能力を持っています。
こうした一連の裏側に秘められた事実を分かった上で、童話と違う“魅惑的な”赤ずきんを鑑賞すると楽しく見れるでしょうね。
ストーリー的には大変楽しく見れたのですが、CGの作りが雑な点が気になったので、今回は…
「評価 ★★★★★ ★★☆☆☆ 70点」
(あらすじ)☆ネタバレ注意!
美しく成長した年頃のバレリー(アマンダ・サイフリッド)は、両親によって村一番の裕福な一族の跡取りヘンリー(マックス・アイアンズ)との婚約が決められたことを知らされる。
だが、彼女には幼馴染みで木こりのピーター(シャイロー・フェルナンデス)という、将来を誓い合った恋人がいた。
2人はすべてを投げ捨てて駆け落ちを決意するが、血のように真っ赤な満月の夜、すべてが一瞬にして変わってしまう。
バレリーの姉が何者かに殺されたのだ。
この村では長年に渡って、動物の生け贄を捧げることで平和を保っていたが、“それ”は協定を破ったのだ。
怒りに震え、復讐に燃える村人たちは、魔物ハンターとして名を馳せるソロモン神父(ゲイリー・オールドマン)を村に招く。
だが、やって来たソロモンは、村人たちに思いもよらぬ事実を告げる。
犯人=“それ”は満月の夜だけ狼に変わる人狼だというのだ。
“それ”は正体を隠したまま村に紛れているというソロモンの言葉によって、疑心暗鬼を募らせる村人たち。
次々に犠牲者が増えるなか、パニックに陥ってゆく。
そして13年に一度の赤い惑星と月が並ぶ夜。
血のように赤い月の下でついに“それ”は姿を現す。
そして、“それ”はバレリーに話しかける。
“俺はお前をよく知っている。一緒に来い”。
一体“それ”は何者なのか?
手がかりはダークブラウンの瞳だけ。
愛するピーターなのか?婚約者のヘンリーか?それとも……?
“それ”の目的がバレリーを連れ去ることだと知ったソロモン神父は、彼女を囮にして広場に拘束する。
危機が迫る中、ついに“それ”の正体が暴かれるが……。
★Face bookもよろしく!→http://www.facebook.com/#!/hironobu.higa
Posted by no-bu at 08:43│Comments(4)
│映画
この記事へのコメント
週末はこれも、だな!
Posted by samura at 2012年01月28日 08:48
at 2012年01月28日 08:48
 at 2012年01月28日 08:48
at 2012年01月28日 08:48佐村さん
メタルヘッドとは、全く毛色の異なる作品。
ある意味、続けてみると、そのおもしろさが良く分かるでしょうね。
メタルヘッドとは、全く毛色の異なる作品。
ある意味、続けてみると、そのおもしろさが良く分かるでしょうね。
Posted by no-bu at 2012年01月28日 19:13
at 2012年01月28日 19:13
 at 2012年01月28日 19:13
at 2012年01月28日 19:13両方ともレンタルされてた・・・(泣)。
Posted by samura at 2012年01月28日 20:03
at 2012年01月28日 20:03
 at 2012年01月28日 20:03
at 2012年01月28日 20:03あらまあ…(^^;)
Posted by no-bu at 2012年01月29日 07:43
at 2012年01月29日 07:43
 at 2012年01月29日 07:43
at 2012年01月29日 07:43